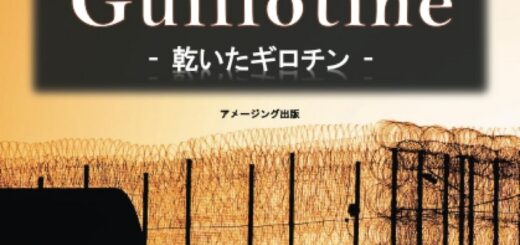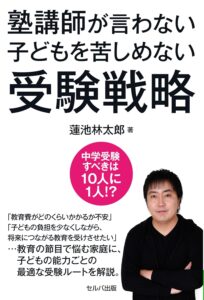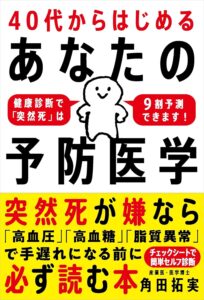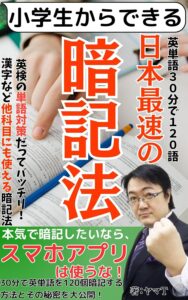宿題しない…怒る以外に何ができる?『世界標準 AO式子育て』で答え合わせ
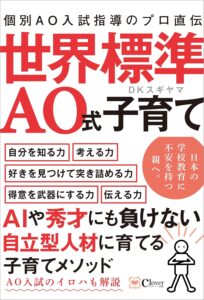
引用:Amazon商品ページ
⚪︎ブログ運営者kimkim紹介
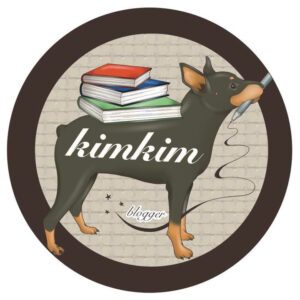
読書家:1日1冊以上読書、累計1000冊以上読了、元々は読書大嫌い
小説やビジネス書、エッセイなど幅広いジャンルを扱い、読書の魅力を発信しています。
皆さんが気になる本を見つけられるよう、詳細に書評をします。
○教育熱心な親御さん
○お子さんがAO入試を控えている人
・
「また宿題やってないじゃん…!」
つい声が大きくなっちゃう。あるあるですよね。
私も正直、焦ると「早くやりなさい!」って連呼しがちでした。
でも怒っても進まないし、親子の空気は悪化…。
そこで読み直したのが『世界標準 AO式子育て』。
これ、怒鳴る代わりに“仕組み”で回すヒントがぎゅっと詰まってました。めちゃくちゃ実用的!
皆さんも一緒に“怒らない回し方”をアップデートしませんか?
目次
『世界標準 AO式子育て』とは何か
著者DKスギヤマのプロフィール
著者はビジネス・プロデューサーのDKスギヤマ(杉山大輔)さん。
慶應SFC出身、MBA取得、4人の父でもあります。
ご本人はAO入試で慶應SFCに合格し、⻑男も2021年に同じくAOでSFCへ。
教育×起業の現場で子どもたちの伴走を続けてきた実践派です。
本書が提唱する子育ての考え方
AO入試って、“テストの点”だけじゃ測れない力をみますよね。だから家庭でも、
-
自分の好き・得意・やってみたいを言語化
-
小さく試して成果物(作品・記録)を残す
-
人前で伝える(プレゼン・発表)
この循環を回す。これが「AO式」。合格だけがゴールじゃなく、“生きる力”を鍛えるのが肝なんです。
なぜ「世界標準」なのか
海外の入試やキャリアでも、ポートフォリオ、課外活動、探究、プレゼンは当たり前。
点数一本勝負じゃないから、自分のテーマを掘り下げ、成果で語る姿勢が求められます。
日本でもその波が来ている。だから“家庭内からグローバル基準で育てる”がテーマなんですよね。
なぜ子どもは宿題をやらないのか
子ども視点の心理的背景
宿題を後回しにしちゃうのは“怠け”だけじゃありません。多くはこの3つ。
-
自律性の不足:「やらされ感」MAXだとやる気はシュン…
-
有能感の不足:難しすぎて「無理ゲー」に見える
-
目的の不明確さ:「なんで今これ?」が腑に落ちない
つまり、“やる意味”と“自分で決めた感”が薄いと、そりゃ動けないんです。
親がついやりがちなNG行動
これ、私もやっちゃうんですが…
-
「早くやれ!」の命令オンリー
-
終わってないときのねちねち説教
-
兄弟・友だちとの比較ジャブ
-
親の不安をそのままぶつける監視モード
どれも“自律性”を削りがち。短期的には動いても、長期的には逆効果です。
怒ることのリスクと悪循環
怒る→子どもが防御(反発/回避)→さらに怒る…の地獄ループ。
宿題=罰の連想が定着すると、学び自体を嫌いになっちゃう。
怖いのは「やればできるかも」の芽がしぼむこと。
ここ、親の踏ん張りどころです。
AO式子育てを家庭で取り入れる方法
ステップ①:まず親が変わる
「親が変わると、子どもが変わる」は本当に真理。私が効いたと感じたのはコレ。
-
ゴールを“自立”に置き直す:テスト点より「自分で決めて回す子」に
-
期待の言語化:「結果よりプロセス」「挑戦を称える」を先に宣言
-
役割を“監督→伴走者”へ:指示を減らし、問いを増やす
-
ミスは学びの材料:「次どうする?」で未来志向に
親が“安心安全の土台”になった瞬間、子どもは一歩前に出ます。
ステップ②:日常会話の見直し
怒る代わりに、3つの問いで回します。
-
何をやりたい?(今日のミッション)
-
なぜそれ?(意味の接続)
-
どう試す?(方法の具体化)
会話のコツは“短く・具体的・選択肢付き”。
-
「国語は10分だけ音読と5分要約どっちがいい?」
-
「終わったら自分に★をつける or 私に1分プレゼン、選ぶ?」
称賛は行動に紐づけると効果大。
「早くやってえらい」より「10分で区切った工夫、ナイス!」が響きます。
まとめ:怒らずに育てるヒント
本書から得た親としての気づき
-
宿題は目的じゃなく手段。志や好奇心につながるように意味づけをする
-
小さく試して形に残す。成果物=自信の貯金
-
発信が学びを締める。1分プレゼンで理解が深まる
AO式は“合格テク”に留まらず、生き抜く力の家庭トレーニングだと腑に落ちました。
子どもと向き合う姿勢の変化
私は「監視・指示」から「問い・設計」へ。
正直、完璧にはできません。忘れてお菓子食べちゃう日もあります。笑
でも仕組みがあると立て直せる。怒鳴らないで済む。それが一番の収穫でした。
宿題が進まない夜ほど、怒るより仕組みで回す。
『世界標準 AO式子育て』は、その“家庭内オペレーション”の教科書。
皆さんもぜひ読んでみてください!
私も引き続き、家の“学びシステム”をアップデートしていきます。